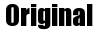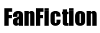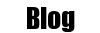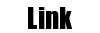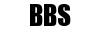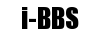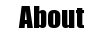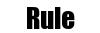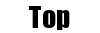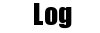「文通…しませんか?」
朝からどんよりとした、今にも雪が降りそうな天気だった。
別に待ち望んでいたわけでもないのに、昼を過ぎても一向に降り始めない氷の結晶を今降るか、 もう降るか、といつの間にか僕は待つようになっていた。
授業の終わりを告げる鐘がなり、にわかに騒がしくなる教室。
退屈な授業が終わった事で解放されたクラスメートたちが放課後の予定を立てている中、 僕はそっと教室を出て行った。
人が溢れる校庭を抜け、気まぐれに僕を待っている彼女を見つけると、僕らは互いに軽く挨拶をすると一緒に歩き始めた。
夕方の商店街。
街灯の明かりが点き始め、たまたま通りがかった今時珍しい文房具屋を見て、僕はシャープペン芯が切れているのを思い出した。
すぐ終わるから、と連れに待っているよう頼み、通行人の間を抜けて、ちょっと急いで店に駆け込む。
あんまり待たせると文句を言われるから、僕は出来るだけ急いで目的の物を探す。
見るからに個人商店な感じの狭い店内で、それを探すのにそれ程時間は掛からなかった。
財布から小銭を素早く取り出し、会計を済ませて店を出た。
するといつの間にか降り始めた雪がうっすらと通りを白く染め始めていて、 僕は未だ見慣れない白い絨毯の上を、さっきまで急いでいたというのに、今度は心を躍らせながらゆっくりと踏みしめた。
そんな帰り道、突然女の子の声に呼び止められて立ち止まる。
振り向いた先に居た彼女は、雪と同じ様な白い肌を薄紅に染めて、一通の封筒を差し出した。
「あっ、ええっと、と、突然ごめんなさい。」
さっきよりも更に顔を真っ赤にしてばたばたと手を振ってて、慌ててるその様子が可愛くて、つい口からくすっと笑いが零れる。
すると彼女はもっと顔を赤くして、とうとう顔を伏せてしまった。
「ゴメンゴメン。」
「もうっ!!」
僕が謝ると今度はすねた様に顔を彼女はそむけた。
コロコロと変わるその表情に、僕は何故だか嬉しくなってまた笑ってしまった。
「何笑ってるんですか!?」
「いや、可愛いなって思ってつい。」
自分でも歯の浮くようなセリフだ、と思った。
彼女の赤くなりっ放しの顔を見ながら、僕は時間の経過を噛み締める。
前ならこんな言葉絶対言えなかっただろうな……
「それで文通って?」
「えっ?あ、はい、あの……」
言葉が続かず、彼女はうつむいて唇を噛み締めた。
続きを言おうと口が開いてはまた閉じて、それを僕は急かすでも無く、ただじっと待っていた。
「えっと、その、センパイ格好良いから、そのぉ、こ……」
「こ?」
「こ……お、お友達になってくれませんか!?」
…辺り一帯に聞こえるくらいの大声で叫んだ。
もう夜になろうかという時間で、人も多くなりかけてる通りでそんな大きな声で叫んだら結果なんて分かりきってる。
仕事帰りのOLさんや、これから街中に消えていこうと考えてるカップルたちがくすくす笑いながら通り過ぎていった。
そして今、彼女がどんな状態かも簡単に想像できる。
まさかマンガみたいな事をするとは思わなかったけど。
「……」
思った通り真っ赤なまま口をパクパクと動かして固まってる。
昔と違って豊かな表情を見せてくれる彼女の姿に、また時の流れを感じながら僕は動かない彼女に助け舟を出した。
「えっと、僕と友達に?」
「は、はい!!
で、でもダメですよね…?きちんと話した事も無かったのに急にそんな事言われても困りますよね……」
「いいよ。」
「そうですよね、やっぱりダメですよね……」
「ダメなの?」
「ダメなのってそりゃそう……っていいんですか!?」
ホントマンガみたいだ。
昔と性格変わったとは思ったけど、ここまで変わってるとは思わなかった。
僕が頷くと、彼女は驚いた顔をあっという間に笑顔に変えた。
それでもまだ半信半疑なのか、早口で一息に疑問を口にする。
「で、でもセンパイ、私の事知らないのにいいんですか!?
知らない人について行っちゃダメだってご両親に教わらなかったんですか!?」
「いや、別についていくわけじゃないし。
それに僕は君の事知らないわけでもないよ?」
「え?」
予想外だったみたい。
きょとん、として僕の顔を見つめる。
そんな様子がまた少し可愛かった。
「シンジ、そろそろ行くわよ〜?」
「あ、ちょっと待って。」
アスカに呼ばれた。もう行かなきゃ。随分待たせちゃったし。
「ゴメン、もう行かなきゃ。」
「え、ええ……」
「それじゃあすぐに返事を書くから。
またね、碇レイさん?」
the bEautIfuL WORLD
レイと別れたシンジはアスカの元に走り寄った。
街灯の柱に背中を預けて、アスカは冷えた手を温めようとコートのポケットに突っ込み、 時折手に息を吹きかけながらシンジを待っていた。
色白な鼻が少し赤く染まり、口から吐き出される息が白く光って散っていく。
金色の髪には雪がわずかに積もり、街灯からの光がそれを一層白く際立たせていた。
「遅いわよ。」
「ゴメン。」
アスカの文句に謝りながら、シンジはそっとアスカの頭に乗った雪を払ってやる。
その間、アスカはポケットに手を突っ込んだまま黙って待っていた。
「ふ〜ん、アンタも結構気が利くようになったわね。」
「そりゃそうだよ。僕だって少しは成長するよ。」
「どうだかね。」
肩をすくめて、アスカは先程より更に積もった雪道を歩き始める。
シンジも手を自分のコートのポケットに突っ込んで、アスカの横を少し距離を置いてついて行く。
二人はずっと無言で歩き続けた。
交互にお互いの口から白い息が漏れる。
雪は強くなることも無く、大きな牡丹雪がゆっくりと二人の足元を濡らしていった。
いつしか街中から離れ、閑静な住宅街へと景色を変える。
雪ではしゃぐ子の姿も無く、ただただ静寂が通りを支配する。
陽は完全に落ち、所々にある街灯だけが道を明るく照らしていた。
「ねえ……」
アスカに声を掛けられて、シンジはようやく視線を上げた。
だがアスカの顔はうつむき気味で、視線は足元に固定されたままだった。
「レイはどうだった?元気だった?」
「うん、元気だったよ。昔じゃ考えられないくらい明るかった。」
「そう……」
少し顔を上げてアスカは微笑んだ。
しかしまたすぐに視線を落とすと、表情をわずかに歪ませた。
それにシンジは気付いたが、何も言わず、黙って雪道を踏みしめる。
ザク、ザクと足音が耳に響いた。
「もう少し話したかったんだけどね。」
「だってじっと待ってるのって寒いのよ。すっかり体が冷えちゃったわ。」
「だからもう少し厚着しろって言ったんだよ。今日は雪が降るって予報で言ってたから。」
「はいはい。私が悪かったわよ。」
そう言うとアスカは、冷えた体を温めようとコートの襟を立てて首をうずめた。
切れかけた街灯がチカチカと点滅した。
「それで、何の用だったの?」
「これ。」
シンジはポケットの中からレイから受け取った手紙をアスカに見せる。
真っ白の封筒に、可愛らしい天使が描かれたシールで封がされていた。
「ラブレター?」
「そうだと思ったんだけどね……
文通しませんか、だって。」
「文通ぅ!?」
素っ頓狂な声を上げてアスカは目を丸くし、そして大きな溜息を吐き出す。
「このご時勢に文通ねぇ……
あの子いつの時代の子よ?」
「そう悪いものでもないと思うよ。
手書きでもメールじゃ伝わらないものがあると思うけど。」
「そりゃ否定しないわよ。
人の心はデジタルじゃないもの。」
「ゼロとイチじゃ表せない、か……
ホントにその通りだね。」
アスカが立ち止まり、シンジもまた足を止めた。
白い、深い息を吐き出すと、アスカは空を見上げる。
本来ならば今日は綺麗な満月が顔を覗かせていたはず。
だが雪はシンシンと降り続き、分厚い雲が月を隠していた。
「それで、どうだったの?」
声を掛けられてレイは視線を窓から正面へ向けた。
そこにはマナがやや垂れめな瞳を輝かせて、レイの答えを待っていた。
「どうだったって、何が?」
「だ〜か〜ら〜!昨日綾波センパイに告白したんでしょ!?」
「そうですよ。結果を楽しみに待ってたんですよ?」
マユミも何処から現れたのか、レイの顔を覗き込む。
長い黒髪に理知的な眼鏡をかけた彼女は普段は落ち着いた雰囲気の少女なのだが、今はマナ同様に、 どういう訳か周りに全く話の出ない恋話に興味津々の様だ。
椅子に座っているレイに視線を合わせる様に屈みこみ、話の続きを今か今かと待っている。
窓からの光に反射した眼鏡がやや怖い。
「え〜と……」
二人に迫られてレイは昨日の事を思い出した。
しかしその途端、レイの顔は真っ赤に染まった。
「お?その顔は何かあったのかな〜?」
「ま、まさか!?告白したその日にそんなところまでいってしまったんですか!?」
「ち、違うわよ!!」
二人の想像の内容に思い至ったレイは、赤い顔のまま全力で否定する。
だがそれはやぶ蛇だった。
レイが叫ぶと同時にマナとマユミはニヤリと口元を歪ませると、更にレイに詰め寄る。
はめられた、と気付いた時にはすでに遅し。
「あっれ〜?レイちゃんは何を想像したのかな〜?」
「そんな…やっぱり綾波センパイと……!!」
「だ〜か〜ら〜!!違うって!!」
「じゃあ何でそんなに顔赤いのよ?」
マナにつっこまれてレイは答えに窮した。
かと言って昨日の内容をそのまま答えるのも恥ずかしい。
レイは二人の顔を見た。
どう見ても、このまま見逃してくれそうも無い。
じりじり、と二人のにやけた顔が近づいてくる。
口にこそ出してないが、二人の顔はどう考えても「さあ、吐いて楽になってしまいなさい!」と言ってる様にしか見えない。
「それで、どうだったのかな?」
レイは観念した。
「ぶわぁはははははははははははは!!」
第壱高校2−Aの教室中にマナの爆笑が木霊した。
昼休みでそれなりに人が残っていて、皆突然聞こえ始めたマナの笑い声に振り返るが、マナはその視線を一向に気にせず笑い転げた。
レイの机をバンバンと叩き、腹を押さえて完全に呼吸困難になっている。 そこに容赦は無い。
レイは真っ赤なまま顔を伏せるしか出来ない。
色白な彼女だが、今はこれでもか、と言うくらい全身を赤く染めていた。
「だ、ダメですよ、マナさん。そ、そんな笑っちゃ……」
マユミがマナを諌めるが、そう言う彼女自身が肩を震わせていては説得力など無い。
それでも何とか笑いを堪えているところに彼女の人となりがうかがえはするが。
「ぷ、く、くくくくく……」
無駄な努力かもしれない。
「あ〜すっきりした。」
10分ほどひたすら笑い続けたマナは、発作が収まるとケロッとした顔でそう言ってのけた。
無論そこに罪悪感などカケラも無い。
「だから話すの嫌だったのに……」
「いやぁ、だってこれは笑うところでしょ?
ラブレター渡して告白しようとしたら直前で怖気づいてついつい文通しようだなんて言ってしまって でももう一回勇気を振り絞ってちゃんと告白しようとしたけどやっぱりヘタレて通りの真ん中で友達になってくださいって 大声で叫んだなんて話、笑い話にしかなんないわよ。」
「……わざわざ人の恥ずかしい話をもう一度繰り返してくれてどうもありがとう。」
ジト目でマナを見ると、レイはプイッと外の方を向いた。
「はいはい、悪かったわよ。
それで、綾波センパイは何だって?OKって?」
「うん、よろしくって言ってくれた。」
それでもレイはシンジにOKを貰った事が嬉しいのか、すぐに破顔した。
そしてその時の様子を事細かに二人にしゃべりまくる。
だがそれもわずかな事で、次の瞬間には顔を曇らせた。
その変化にマナもマユミも、お互いの顔を見合わせた。
「どうしたの?」
「いや、別に……」
マナの問いかけにも力無く応える。
レイのその様に、マナは腰に手を当てて一つ溜息を吐いた。
「嬉しそーに話してたのに急に落ち込んだりして。
気にならないはずが無いわよ。」
「そうですよ。何か綾波さんの事で気になるところでもあるんですか?」
心配そうに二人が尋ねるが、レイの口は重い。
(いっつもそうなのよねぇ……)
マナは内心でまた溜息を吐いた。
マナ・マユミとレイはもう随分長い付き合いになるが、いつもレイは悩みを中々話そうとしない。
そのくせに表情や態度にそれが出やすい。
昔は無理に聞き出すのも悪いと思ってそっとしていたが、今では無理やりにでも聞くようにしている。
そうしないと自分の中でどんどん深みにはまっていくから。
去年にも似たような事があったし、中学生の時にも両親とうまくいかなくて話を聞いてあげた事があった。
小学生の時も、幼稚園の頃にも……
(あれ?)
そういえばレイと知り合ったのはいつだろうか?
マナはそれをはっきりと思い出せない。
(ま、それだけ長い付き合いだって事よね。)
「えっと……」
マナが記憶を探っていた間、マユミがレイに色々話しかけていたのだろう。
ようやくレイが口を開き、マナは意識をレイの方に移した。
「綾波センパイって…やっぱり彼女居るのかな……?」
「でもレイの手紙受け取ってくれたんでしょ?」
「うん…でもそれはセンパイが優しいから……」
「何か思い当たる事でもあるんですか?」
マユミが尋ねると、レイの顔から表情が消える。
能面の様なその顔に、二人の背中にわずかに緊張が走った。
しかしまたすぐに綺麗に整えられた眉が歪み、悲しそうな表情を浮かべた。
「センパイ、昨日女の人と一緒だったみたい……綺麗な外国の人で、センパイの事、シンジって呼んでた……」
「えっ?でも確か綾波センパイって彼女いないって話じゃ……」
「外国の人だったら例えばホームステイに来てる、とかじゃないの?」
「う〜ん……」
そう言われてもレイは納得できない。
チラリとしか見えなかったが、シンジを待っていた女性はレイの目から見てもかなりの美人だった。
呼び方からしてそれなり以上に親しいように思える。
そしてシンジもその女性に親しそうだった。
「ん〜、そんなに気になるんなら直接聞いてみれば?」
「え?」
顔を上げてマナを見ると、マナは教室の入り口を指差していた。
その方向にレイも顔を動かす。
「……!」
レイは絶句した。そして頬が紅潮する。
慌てて立ち上がり、その際椅子を倒してガターンと大きな音を立てた。
レイの椅子は教室の窓際にあり、入り口に行くにはいくつもの机の間をすり抜けなければならない。
あちこちの机に足をぶつけ、その度にガタガタと机をずらして笑顔で手を振るシンジの元へレイは駆け寄った。
直線にしてわずか数メートルの距離。
だがレイがクスクスと笑うシンジの所へたどり着いた時は激しく息を切らしていた。
「大丈夫?」
「は、はひっ!!も、問題ありません!!」
声を裏返し、自分の妙な言葉遣いに更にレイは顔を赤くする。
教室の中からも声を潜めた笑い声がレイの耳に届いた。一人だけまた爆笑しているみたいだが。
「そ、それでセンパイ、どうしたんですか?」
気を取り直してシンジに尋ねる。
するとシンジは一枚の封筒を取り出して、レイに差し出した。
「これは?」
「昨日の返事だよ。本当は郵送しようと思ったんだけどね、碇さんの住所がどこにも書いてなかったから。」
それはそうだ。住所など書いているはずがない。ラブレターのつもりで書いたのだから。
レイは茶色い封筒を持ったシンジの顔を上目遣いに見た。
そこにはレイが知っている通りのシンジがいた。
決して特別格好良くは無いが、優しそうな顔。
自分の思いはちゃんと伝わったんだろうか?
付き合ってもらえるんだろうか?
それともダメなんだろうか?
いや、こうしてすぐに返事をくれるって事はきっとOKに違いない!
でもこんな茶封筒で返事?
ていうか、何で手紙で返事?
レイの頭が混乱してくる中、シンジが声を掛ける。
「ゴメン、本当はもっとちゃんとした封筒で渡したかったんだけど、家にこれしかなくて。」
「い、いえ、全然構いません。」
「また返事送ってね。住所は中に書いてるから。」
「はい?」
返事を送る?
理解できないシンジの言葉を聞きなおそうと、レイは口を開きかけたが、ここで昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴り響いた。
「それじゃ、楽しみにしてるから。」
「あっ、ちょ、ちょっとセンパイ!!」
レイの静止の声も聞こえないのか、シンジはそのまま去っていった。
その後姿をレイはボーっと眺めていたが、手に残る手紙を見ると表情を緩めた。
(ま、いっか……)
返事は良く分からないが、こうして直接すぐに返事を持って来てくれたという事は、少なくとも多少は脈はあるのだろう。
レイはそう考えることにした。
そう考えると、早く手紙の内容を知りたくなる。
飾り気の無い実用的な封筒。
それがレイの知るシンジの実直な性格を表している様に思える。
「ほ〜ら。ちゃっちゃっと席に着きなさい。授業を始めるわよ〜?」
「あっ。」
担任であり、次の英語の授業の担当でもあるミサトに急かされ、レイは慌てて席に戻る。
クラスメートの微かな笑い声が聞こえてくるが、レイは気にならなかった。
ポケットに入れた手紙を軽く握り締める。
カサ、と小さな音が聞こえた。
(そういえば……)
肝心の事を聞いていない。
シンジに彼女は居るのか。
その事を思い出した時、赤い女性が頭をよぎった。
その日の夜、レイは学校を出ると真っ直ぐに家へと向かった。
第三新東京市の郊外に位置する高層マンション群。
その中の一つがレイの自宅である。
マンションのエントランスに駆け込んで、エレベーターのボタンを押す。
最上階に上がっていたエレベーターが降り始める。
階数を示す数字が一つ、また一つと減り、レイの待つ一階へと近づく。
だがゆっくりとしか数字は減らない。
腰に手を当てて、靴をカツカツと鳴らすが、当然そうしてもエレベーターの速度が速くなるわけではない。
更には途中で誰かが乗ったのか、エレベーターが止まりしかも一向に降りてくる気配が無い。
レイは再び駆け出した。
エレベーターのすぐ隣にある階段の一段目に足を掛けると、一気に走り出す。
レイの体が飛び上がる。
階段を踏み抜かんばかりの、渾身の力を込めて床を蹴る。
踊り場は手すりを掴んで右足を軸に回転。
速度を落とさずにそのまま次の階へ!
オリンピック選手も真っ青な速度でレイは階段を駆け上る。
だが、レイの家はこのマンションの九階にある。
加えて、レイはどちらかと言えば体育会系の人間ではない―――親しい人から見れば明らかに文化系である。
走り始めは本人か?と疑いたくなる勢いだったが、三階を過ぎた辺りから徐々にスピードは落ち始め、 九階に着いた時には今にも倒れんばかりの様子だった。
それでも汗だくのまま何とか家の前に到着すると、レイは汗を拭う事もせず自分の部屋に飛び込む。
カバンから封筒を取り出し、カバンはそのままベッドへ。
部屋の扉に鍵を掛け、丁寧に封筒の封を開けてシンプルな便箋を取り出す。
―――ええっと、綾波シンジです。―――
極分かりきった事から始まり、レイの口からつい笑いが零れる。
(センパイらしい……)
そんな事を思いながら続きを読み進める。
―――お手紙ありがとう。何だか不思議ですね。 こうして世の中にネットワークが広がっているのに手書きの手紙でやり取りをするなんて。―――
確かに。
今更ながらレイは思った。
携帯もあるしパソコンもある。メールなんて一番ありふれてるのに、何故自分は文通なんて言ってしまったんだろう?
前の日に読んでた恋愛小説の所為かな?
(でも……)
結果として良かった。
こうしてセンパイの字の癖や、文からセンパイが少し見えてくる気がする。
センパイという人が近くにいる様に感じられる。
人と人の触れ合い。
今までそんな事を意識した事は無かったが、そう考えてレイは心が温かくなるのを感じた。
心の内の温もりを胸に、レイは手紙に目を移す。
いつシンジからの告白の返事が書かれてるのか。
ドキドキしながら手紙を読み進めた。
手紙の礼で始まり、いかに手紙をもらった事が嬉しかったか。
それが便箋の上で踊るシンジの字からもレイは読み取れた。
しかし、肝心の答えが出てこない。
一行進み更に一行進み、最後まで読み終えてもそれらしい事は何処にも書かれていなかった。
(何で?)
確かに自分は書いたはずだ。
夜中にあまりの恥ずかしさにもだえながら、自分のシンジに対する気持ちを。
その結果が怖くもあり、また楽しみでもありながら、一人で読もうとマナとマユミの誘いも断って帰ってきたのに。
疑問と落胆と、そして安堵がグルグルと頭を巡る。
手紙を見つめ続けること数分。
だが肝心の自分が最も欲していた答えが見つからない。
そこでレイの頭の中で一つ、思い当たる事が浮かんだ。
(もしかして……気付いてない……?)
じっくりと、思い残す事無く想いを手紙につづってシンジに渡したつもりだ。 それもくどいくらいに。
しかし、その中で一つだけ書き忘れた事に思い至った。
好きだ、という言葉を。
(もしかしなくても、センパイって物凄く鈍感?)
レイは急速に体の力が抜けるのを感じた。
脱力して机に突っ伏し、盛大に溜息を吐き出す。
証拠は無いが、思い至った考えに妙に納得できてしまう。
(ま、いっか……)
落ち込んでいてもしょうがない、とレイは頭を切り替えた。
確かに返事はもらえなかったが、シンジと二人っきりの「会話」を出来るというのも悪くは無いのかもしれないし。
直接会えるのとは違うが、これはこれでシンジの人となりを知る事が出来るのだから。
むくり、と体を起こすと女の子にしては飾り気の無い棚から、天使のイラストが描かれた便箋を取り出す。
そして機能的な鉛筆立てからペンを取ると、レイは返事を書き始めた。
が、すぐに自分が汗臭いことに気付き、一度ペンを置く。
(先にシャワー浴びよっかな。)
ずっと走りっぱなしだったから当然か。
気分を変える為にも、一度お風呂に入るのもいいかもしれない。
そして出た後、返事をゆっくり書こう。その方が落ち着いてかけるかもしれないし。
シンプルなタンスから下着を取り出して、浴室へと向かう。
蛇口をひねり、やや熱めのお湯が張りのあるレイの肌を流れ落ちる。
汗で大分冷えていたのか、思った以上の熱にレイの体が震えた。
だがそれも次第に収まり、心地よく体を温めていった。
目を閉じ、逸る心を落ち着けるかの様にじっくりとレイはシャワーを浴びる。
十分に温まり、浴室を出て丹念に体を拭き上げていく。
少し火照った体から冬の寒さが程よく熱を取り去る。
機嫌良さそうに鼻歌を歌いながらレイは服を身につけていくが、その時ふと赤い姿が頭をよぎった。
昼に確認出来なかったシンジの彼女。その事が再び首をもたげ、レイを冷やしていく。
手を繋いで楽しそうに歩くシンジ。笑顔で彼女と話すシンジ。そして彼女と唇を重ねるシンジ。
レイは頭を振って想像を振り払おうとし、急いで部屋へと向かう。
ペンを持ち、便箋に文字を一心不乱に走らせる。
だがその光景は手紙を書き始めてからも消えなかった。
「んん……」
カーテンの隙間から差し込む光と、頬に感じる固い感触にレイは目を覚ました。
体を起こし、辺りを見回す。
そこはシンプルな配置の自分の部屋。ただその視界には自分のベッドが含まれていたが。
「そっか…返事書きながら寝ちゃったんだ……」
朝は強いが、代わりに夜は滅法弱い。
気が付かないうちに机で寝てしまったらしい。
部屋に掛けられた時計は七時を指している。いつもよりかなり遅い時間だ。
間に合わない時間では無いが、少し準備を急いだ方がいいかもしれない。
椅子から立ち上がり、制服に着替えようと壁の方に歩き出す。
だがその途中で腰がくだけ、膝をついてしまう。
(風邪引いたかな?)
そう言えば少し頭がボーっとしてる気がする。
暖房は効かせていたが、真冬に何も掛けずに寝ては風邪を引くのも当たり前かもしれない。
額に手を当ててみるが、熱は無いようだ。
とりあえず、といつも通りにレイは制服に着替えて、ダイニングへ足を向けた。
綺麗に整頓されたシステムキッチン。
流しには、昨夜レイが食事を取った食器がそのままあった。
両親は昨夜は帰ってこなかったらしい。
二人ともどこかの研究所に勤めていて、向こうに泊まる事など珍しくも無い。
だから昨夜も一人分しかレイは料理を作らなかったのだが。
朝食を準備しようと、レイは炊飯器の蓋を開ける。
が、そこには米は一粒も残っていなかった。
(しまった…昨夜全部食べちゃったんだっけ……)
手紙を書くのに必死で、朝の分を炊くのをレイは忘れていた。
こういう時に限ってパンも何も無い。
食卓の椅子に座ると、ドッと疲れが出てきたような気さえする。
体を動かすのさえ億劫に感じ、気だるくなってきた。
(…今日はもう学校休も……)
お昼前になったら病院に行って、薬を飲んで、今日は一日大人しくしていよう。
ゆっくり立ち上がると、今度は布団で寝る為、レイは部屋へ戻って行く。
制服を脱いでパジャマに着替え、ベッドの布団をめくる。
一旦は足を布団の中に入れるが、机の方を見ると、体をそちらへと向けた。
そして机に広げられた一枚の紙を大事そうに胸に抱えると、真白な封筒へそれを入れた。
『上気道感染』
これが病院で診断されたレイの病名であった。
大層な名前がついてはいるが、何てことは無い、ただの風邪である。
だがどういうわけか、風邪と言われて最初にレイの頭に浮かんだのがこれであった。
深い意味は無い。どこでその言葉を覚えたのか。
いつか本で読んで、それで知ったのか。
自分の中ではそんな事が書かれているような本は読んだ記憶は無い。
さして気にすることでもない、とレイは病院を出た。
隣の薬局で処方された薬を貰って家へ。
ただの風邪なら今日一日大人しく寝ていればいい。
明日には元気になっているだろう。
そして学校に行って、センパイとまた話して、少しはいい雰囲気に……
もしセンパイに会えなくても、また明日には手紙が届いているかもしれない。
制服にコートを着て、昼前の商店街を歩きながら明日への楽しみに思いを馳せる。
風邪を引いているはずだが、それを考えるとさっきまで重かった体も少し軽くなったような気さえした。
駅前の繁華街を抜け、落ち着いた街並みが広がる。
人混みもいつしか遠ざかり、通りを歩く人の姿がまばらになってきた。
家に向かって歩き続けるレイ。
だがその足が正面から迫ってくる姿を目に止めた瞬間、止まった。
「あっ……」
驚きと共に開かれる目と口。
更に悪い事に、声が漏れた事によって相手もレイの存在に気付いた。
口に手を当てるが時すでに遅し。
レイが驚きの声を上げた対象は、もうレイの目の前に立っていた。
「初めまして、てところかしらね?」
駅の方へ少し戻って、二人は喫茶店に足を踏み入れた。
レイとしてはそのまま立ち去りたかったが、アスカは半ば強引にレイを連れて行った。
アスカは席に着くと、メニューから適当に二人分のコーヒーを選んで注文し、黙ってコーヒーを待った。
平日の昼前の所為か、それともあまりこの店が流行ってないのか、店内に客の姿はほとんど見られない。
レイは緊張からか風邪からなのか、息苦しさを感じていた。
だがそれも注文してそう時間が経っていないのに届けられたコーヒーによって解放される。
アスカはレイとは逆にぼんやりと店に客が居ない理由を考えていたが、多分後者だろうとあたりをつけた。
コーヒーに軽く口をつけながら店内を軽く見渡す。
決して悪くは無いが、無個性な店内。
コーヒーはコーヒーで味はインスタントとそう変わりは無い。
(これならシンジの入れたコーヒーの方がよっぽど美味しいわね。)
ボソッと心の中で洩らす。
流石にそれは口には出さなかったが。
(でも、ホントに雰囲気は悪くないわね……)
静かな店内に流れるクラシックな音楽。
今みたいにゆっくり過ごしたい時にはいいかもしれない。
ただ単に客がいないからそう思うのかもしれないが。
目を閉じ、聞こえてくる曲に聴き入る。
店のBGMにはずっとパッヘルベルのカノンが流れていた。
「あ、あの……」
レイに呼ばれてアスカは意識を正面へと戻した。
そういえば私が連れてきたんだっけ。
レイの顔を見て、アスカは自分たちがここに居る理由を思い出した。
だがそうは言っても特に理由が有った訳ではない。
ただ暇だから街をぶらついていたら、たまたまレイを見つけた。
それで話でもしようかと思って誘っただけなのだ。
「何?」
「いえ、どうして私を誘ったのかと……」
レイの声が尻すぼみに小さくなる。
レイにしてみれば気が気でないのだ。
相手は自分が告白した想い人の恋人なのかも知れないのだから。
手紙を渡した時にも居た。
今こうして声を掛けてきたのは私に文句を言うためではないだろうか。
レイの頭の中で、よくある昼のドラマが再生された。
『アタシのヒロシさんに手を出さないで!』
『フン、アンタには関係ないでしょ。』
『ヒロシさん、あんな女の何処がいいの?』
『ぼ、僕は…』
普段ならこんな事ありえない、と一笑に伏してしまうところなのだが、如何せん、状況が状況だけに笑えない。
「うそをつきました」と言いながら閻魔様に舌を抜かれるのを待つ罪人の様な気分で、レイはアスカからの返事を待った。
「別に。ただ貴女と話したかっただけよ。」
話。
その単語を聞いただけで、レイの鼓動は大きく跳ねた。文字通り太鼓のように。
ゴクリ、と唾を飲み込む。にも関わらずしっかりと喉は粘っていた。
修羅場。
そんな、自分には絶対に縁は無いなどと、根拠の無い自信はなんだったのか。
いつの間にかレイの頭の昼ドラでは、ナイフが出てきて男を女が刺すという血みどろの展開が広がっていたりする。
「私のシンジを取らないで。」
冷たい言葉がレイを抉る。
予想してたとは言え、まさか本当に来るとはレイも思っていなかった。
それだけに鋭利、と言うよりは鈍器で殴られた様に、じわじわと痛みが広がる。
「なんて、アタシが言うとでも思ってるんでしょ、どうせ。」
脱力。
レイが伏せていた顔を上げると、そこには笑顔のアスカが居た。
「あ…あははは……」
もはや笑うしかない。
アスカのセリフを肯定する事も出来ず、レイはまだ熱いコーヒーを一息に飲み干した。
「大方誤解してるんでしょうから言っておくけど、別にアタシとシンジは付き合ってるわけじゃないわよ?」
「そ、そうなんですか?」
なら杞憂だったわけだ。
レイは今度こそ安堵の溜息を吐いた。
「それに、アタシと…レイとシンジは昔はよく一緒に行動してたのよ?」
「えっ?」
レイは自分の記憶を探ってみるが、そんな心当たりは無い。
少なくとここ数年は会った事も無いはずだ。
「ま、アンタは覚えてないでしょうけどね。」
「す、スイマセン……」
「それはともかく、アタシとしては久々に会った訳だから話をしたかっただけよ。」
そう言うと、アスカはまたコーヒーを注文した。
レイも少しは緊張が解けてきたのか、冷たい物を頼む。
ただ口の中がヒリヒリしているからなのだが。
「今何処に住んでるの?」
「あ、ここから十分くらい歩いたマンションです、郊外にある。
今、というかもうずっとそこですけど。」
「へえ、いいとこ住んでるじゃない。」
「あ、えっと……」
「アスカよ。」
よくよく考えれば、レイはアスカの名前を知らない、というか覚えてない。
それに気付いてかアスカが教えるが、その名前を聞いてもレイは何も思い出せない。
ただ、レイの内の何かに引っかかるものがあったが。
「その、アスカさんはどちらに?」
「アタシ?アタシも郊外だけど、もっと活気の無いところよ。」
だからここまで足を伸ばしたんだけど、とアスカは付け加えた。
「アスカさんは高校は何処ですか?」
「ん〜、高校は行ってないわ。」
「え?」
「だってアタシもう大学出てるし。」
「え!?アスカさんって今何歳なんですか?」
「内緒よ。レディーに年齢を聞くものじゃないわ。」
別に女同士だからいいじゃないか、とも思ったが、アスカの目が笑っていなかったのでレイは自粛した。
(でもどう見ても、私と同じくらいよね……)
大学を出てる、という事はもう二十三くらいになるのだろうか。
例え二十三歳であったとしても十分若いのだが、高校生だとしても十分通じそうだ。
それと共に、成熟した女性としての色気も感じさせる。
(私もあれくらい魅力があればセンパイも……)
「ところでさ…」
「ひゃ、はい。」
妄想に没頭していたところに声を掛けられ、レイの声が裏返る。どうも癖らしい。
「今日平日だけど、学校はどうしたのよ?」
「あ、ちょっと風邪引いたみたいで病院に行ってきたんです。」
「風邪?」
「はい、ちょっとフラフラしたんで診てもらったんですけど、どこも悪いところは無いから風邪だろうって。」
「ちょっと、そういう事は早く言いなさいよ!」
「は、はいゴメンなさい。」
急に態度が変わったアスカに驚き、思わずレイは謝った。
その様子にアスカは一度溜息を吐くと、落ち着いて椅子に座りなおした。
「悪かったわよ。
早く帰って寝ときなさい。ここは払っとくから。」
「え、でも……」
「いいからいいから。アタシの気が変わんないうちよ。」
「はあ、なら……」
お願いします、と頭を下げるとレイはコートを持って店を出た。
その後姿を腰に手を当て、仁王立ちでアスカは見送ったが、やがてレイの姿が見えなくなると、力が抜けたように椅子に座り込んだ。
「もう時間はあまり無いのね……」
ポツリと呟くアスカ。
店のスピーカーからは繰り返しカノンが流れていた。
二次創作一覧に戻る