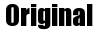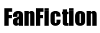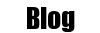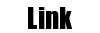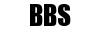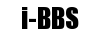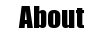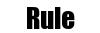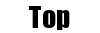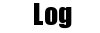ガタン、ガタン、ガタン。
周期的に車体が揺れ、決して大きくない振動が車内の人間を心地よい眠りに誘う。
特別混み合っていない、だがそれなりの人数がリニアに揺られ、ゆったりとしたスペースで少なくない乗客がうつらうつらと船を漕ぐ。
窓から見える景色は、つい十分ほど前までは山林がほとんどであったが、今はビルが増え、夜の闇を切り裂くようにしてネオンが明るい街並みを作り上げている。リニアに並行して走る国道には車が列を成して走り、夜を知らない街を更に明るく染め上げる。
それでも車内と外とでは明るさの程度が異なる。車内と比べると外は厳として夜であり、そこには明確なラインがある。
窓際に座る青年はぼんやりと外の風景を眺めていた。記憶を辿り、目に入って来る景色と記憶との相違点を探り、あれが変わった、ここは変わってない、と一人心の中でつぶやきながら流れる景色を追う。
左から右へと移ろう瞳が視界の端に映る青年自身を捉えた。
容姿は至って平凡。髪は長くも短くもなく、黒い前髪が額を隠している。どちらかと言えば丸顔で、男性だと分かるものの、その柔和な顔立ちからか少し中性的な雰囲気も併せ持っている。
(あまり変わってないな……)
自分の顔を見てため息をつき、ガラスに反射する自分をマジマジと見つめていた事に気づいてもう一度ため息。次いで苦笑。
視線を自分から外して再度街の方へと移す。そして先ほどからしていた記憶との確認作業を再開するが、頭に思い浮かぶ感想は同じだった。
――変わっていない
当然ながら細部は異なる。眼前に広がる街は一度崩壊した街であり、記憶も曖昧だがそれでも何処と無く建物の並びは相似で、それが郷愁を青年にもたらしていた。
たったの一年足らずしか住んでいなかった。だが強烈な一年。青年は懐かしむように眼を細める。
「次は新箱根湯本、新箱根湯本、終点です。ご乗車ありがとうございました。お忘れ物の無いように……」
車内アナウンスを合図として、眠りに就いていた人たちも眼を覚まし降車の準備を始める。網棚から荷物を下ろし、時計を確認したり、早くも席を立ってドアへと向かったりを始める。
青年もその流れに乗って、隣の席に置いていたスカイブルーのリュックを背負う。
リニアが止まり、ドアが開いて乗客たちが一斉に降り始める。空調の効いていた車内にムワッとした空気が流れ込み、人ごみの熱気もあって一気に汗ばむばかりの夏へと季節が変化する。
記憶よりも大きくなった駅は人で溢れ、隙間なくホームからの階段を埋めていった。
階段を降り、駅の構内を抜け、ポケットから切符を出して改札を抜ける。
そこには、消えたはずの街が、以前よりも大きくなって存在していた。リニアの中からもそれは分かっていたが、地面に降り立って見ることで改めてそれを実感する。
ほんのわずかに青年の顔がほころぶ。どこかあどけなさが抜けない、優しい笑顔。青年が少年へと変化する。そしてつぶやいた。
「……ただいま」
卒業
「いらっしゃいませぇ!!」
暖簾のかかった、いささかレトロな雰囲気の居酒屋に入ると威勢のいい声が出迎える。店内にはアルコールと焼き鳥の焼ける匂いが充満し、たくさんの客がそれぞれの席で酒を楽しんでいた。
「いらっしゃいませ。お客様はお一人様でしょうか?」
「あ、いえ、もう先に来てる人がいるんですけど……」
慣れない雰囲気に青年が気押されていると、店の奥の個室になっている所から女性が顔を出す。女性は入口付近でどぎまぎしている青年の姿を認め、整った顔をほころばせて嬉しそうに声を上げた。
「シンちゃ〜ん!こっち、こっちよん!!」
昔懐かしい愛称で呼ばれ、決して狭くはない店内全体に響くほどの大声に客の多くが青年に注目した。
恥ずかしさに顔を赤らめ、声を掛けてきた店員に曖昧な笑顔を浮かべて頭を下げると、そそくさと退散する。
「もう、止めてくださいよ、大声でそう呼ぶの」
「え〜いいじゃない。シンちゃんはシンちゃんなんだからぁ」
青年の抗議も何処吹く風、と言わんばかりにカラカラと笑って女性は流す。
「いや、来た早々災難だったな」
「いえ、ちょっと恥ずかしかっただけですから」
個室に入ると女性の隣りに座る男性が笑いながら話し掛けてきた。その前にはビールの瓶が何本も並べられ、料理の皿もテーブルいっぱいに広がっていた。
「悪いね。コイツが待ちきれなくてな、先に始めてしまったんだ」
「ちょっと、まだ始まってないわよ。ちょ〜ち先に喉を潤してただけじゃない」
女性が抗議の声を上げるが、手に持っているジョッキはすでに八割方無くなっていて、どの料理の皿も減っているのが目に見えて分かる。
姿だけでなく中身も変わっていない事に、青年はわざとらしく深いため息をつき、女性が頬を膨らませると、その年齢に似合わない仕草に今度は苦笑いを浮かべた。
「ま、何にせよ。これでちゃんと始められるな」
「そうですね。お待たせしてスミマセン」
男性が取りなしたところで店員が注文を取りに来て、青年が飲み物を頼もうとするのを遮り女性が声を出した。
「大ジョッキを二つね〜」
「おいおい……」
男性が呆れた風にため息混じりに声を漏らし、青年も苦笑いを浮かべたまま黙ってメニューを閉じた。
程なくしてビールが届き、三人ともジョッキを手にする。
「それじゃ改めて。
久しぶりだな、シンジ君」
「はい、お久しぶりです、加持さん。そして……ただいま、ミサトさん」
「おかえりなさい……シンジ君」
三人の持ったジョッキが音を立てた。
「向こうでの生活はどうだい、シンジ君」
「あ、はい。順調ですよ。きちんと卒業出来そうですし」
加持からの質問にシンジはジョッキを置き、顔を上げる。まだジョッキ二杯目ではあるが、すでにシンジの顔はほんのりと赤くなっていてそれなりにアルコールが回っていることを示していた。
「確か、料理の専門学校だったな。
昔からシンジ君の飯は上手かったが、また更に腕が上がったって事か」
「そんな……大したことありませんよ」
「そぉんな事ないわよぉ。シンちゃんの朝ゴハンは絶品だったわよん。
てコトは……あれから更に美味しくなってるわけね!?ンフフ…今から明日の朝が楽しみだわ〜」
「おいおい、お前はお客さんに朝飯を作らせるのか?」
「いいじゃない。アンタだってアタシのとシンジ君の、どっちが食べたいのよ?」
「そりゃあ、その……なあ、シンジ君」
加持が助けを求めるように視線を送ってきて、シンジはクス、と小さく笑う。
「いいですよ。お二人のお口に今も合うか分かりませんけど」
「さっすがシンジ君!楽しみにしてるわよ!」
「はあ……悪いな、シンジ君」
「気にしないでください、加持さん。僕もお二人に料理を食べてもらうのが嬉しいですし、それに……加持さんもミサトさんも、僕にとっては家族ですから」
「シンちゃん……」
――まだ、家族と思ってくれてるんだ……
ミサトの目尻がじわりとにじむ。溢れそうになる涙を必死で堪え、ミサトは誤魔化す様に手にあったジョッキを一気にあおった。
シンジはその行動の意味に気づかなかったが、隣にいた加持にはミサトの涙がはっきりと見えた。そして意地っ張りな行動に、一つため息をついて肩を竦める。
「……何よ?」
「いや、別に。ただ君も変わらないなと思っただけさ」
「ハイハイ、どーせアタシは何時まで経っても子供っぽいですよ〜だ!」
「そんな、素敵じゃないですか。いつまでも変わらないっていうの。
僕はずっと『ミサトさん』でいて欲しいですし」
「だそうだ。良かったな、ミサト」
「加持さんも、そんなミサトさんだから結婚したんじゃないんですか?」
「はは、こりゃ参ったな」
一本取られた、と頭を掻いて加持もジョッキを傾ける。
そんな加持を見て、そして隣のミサトを見ると、シンジは二人に聞こえるか分からない程度の小さな声でポツリと漏らした。
「いいですよね、家族……」
だがそのつぶやきは二人の耳にも届き、ミサトは思わず加持と顔を見合わせた。
当人のシンジは聞かれた事に気づいていないのか、赤い顔のまま手の中のジョッキを傾けて中身を空にした。
自分のジョッキと他の二人の中身を確認して尋ね、ミサトたちからも了承を得るとシンジは近くを通りかかった店員にビールを三杯注文し、二人に向き直ると小さく笑った。
「お酒ってこんなに美味しい物だったんですね」
「おっ、シンジ君も一丁前に酒の味が分かる歳になったか」
「昔はミサトさんが毎日飲んでるのを見てて『なんであんなに飲めるんだろう?』って思ってたんですけどね。今なら分かる気がします」
「やっとシンちゃんに理解してもらえたのね……」
今更ながらにシンジに理解してもらえたことに、ミサトはうるうると感激の涙を流す。
「ま、こいつの場合は飲みすぎだけどな」
「もしかしてミサトさん、太りました?」
「んぐっ!?」
が、数秒後に見事に石化した。
何かが決定的に壊れた表情を浮かべて固まっているミサトを横目に、加持はやれやれと肩を竦めると、胸ポケットからタバコを取り出した。
「構わないかい?」
「ええ、どうぞ」
次いでライターを取り出し、手元で火が灯る。ジジ、と微かな音を立て、やがてタバコの先端と加持の口から煙が吐き出され始めた。
「やっぱり、それも美味しいから吸うんですか?」
「どうだろうな。もちろん旨いから吸うんだが、それだけじゃないな。
口元が寂しい、というのもあるし、こういう場だと互いが互いを旨く感じさせてくれる。
だが、俺は自分を冷静にさせてくれる、というのが一番の理由だと思ってる」
「自分を冷静に……」
「そうだ。タバコを吸っていると、不思議と考え事に集中できるのさ。これからの事や自分の中の悩み事を見つめ直し、冷静に振り返る事ができる。
自分に何ができるのか、自分が何をすべきなのか。
そうしていると普段は考えつかなかった様ないい考えが浮かんでくる時もあるし、逆に全く何も出てこない時もある。
しかし、そうやって一人で静かに考える時間が人には必要だし、タバコってのはそういう時間を与えてくれるのさ。
そして最後に、肺の中の煙と一緒に自分の中のモヤモヤした気持ちも一緒に吐き出すんだ。
何かを吐き出す時間をくれる、という意味では酒も一緒だけどな」
「お酒も、ですか?」
「ああ、そうだ。言葉にして表すかどうかの違いこそあれ、胸に溜まったモノを吐き出す事ができるのに変わりはないさ。
幸いにしてシンジ君もこうして俺たちと酒を飲める歳になったんだ」
加持はそこで言葉を区切った。それと同時に、タイミングを図ったようにジョッキが運ばれてきてそれぞれの前に並べられる。
加持はジョッキを手にするとシンジの前のそれに当て、杯が少しだけ濁った音を立てた。
「だから俺はともかくとして、ミサトのことをまだ家族だと思ってるなら、悩み事を打ち明けて欲しい。
もし俺がいると話しづらい内容なら席を外すよ」
「リョウジ……」
「そんな……
加持さんの事も家族だと思ってます」
「そうか、ありがとう」
「でも……」
シンジは加持から眼を逸らした。テーブルの下ではシンジの両手が握り締められては開かれ、何度も繰り返される。
加持もミサトも、シンジを急かすことはせず、じっと見つめ続ける。個室内に静寂が訪れ、隙間から漏れてくる他の席の声が、はっきりと聞こえた。
シンジの左手がきつく握り締められ、ジョッキのビールを一度大きくあおった。
大きなため息がシンジの口から吐き出され、ようやく言葉を口にし始める。
「実は……卒業したらアスカに結婚を申し込もうと思ってます」
「そうか……
それにしちゃ浮かない顔だな?」
加持の問い掛けにシンジは小さくうなずく。
「不安かい?」
「そう……ですね。正直、怖いです」
「大丈夫よ。何だかんだ言いながらも上手くいってたじゃない?
まだ一緒に住んでるんでしょ?アスカもシンちゃんのあ・い・の・こ・と・ば、きっと待ってるわよん」
「あ、いえ。今はアスカとは別々に住んでるんです」
「えっ?そうなの?」
「はい。僕が入学するのに合わせて、少し距離を置きたいって言って……」
「なるほど……アスカらしいわね」
「まだ彼女は大学にいるのかい?」
「ええ。今は大学院に進学して、結構研究室に泊まり込んだりもしてるみたいです」
「それでも定期的に会ったりはしてるんでしょ?」
「それはそうですけど……
でも最近は会う頻度も減ってきてますし……
その、僕は学校を卒業するのに合わせて結婚を申し込もうって決めてたんです。
卒業したら小さなお店を開いて、アスカと一緒にやっていけたら、って思ってたんですけど……」
「最近になってアスカが離れていってる気がして不安だと、シンジ君はそう思うんだな?」
「はい……」
シンジは大きくため息をついて、そして喉を鳴らしながらビールを流し込んだ。
大分酔いが回ってきているのか、ジョッキを持った手が覚束無く、ガチャン、と大きめの音を立ててテーブルに置かれた。
「正直、僕は分からないんです。どうしてアスカが僕なんかとずっと一緒にいてくれるのか」
「シンちゃん……」
「こんな風に、少しアスカと距離ができただけで怖くなるくらい僕は情けない男です。
アスカは美人だし、頭も良くて、性格も昔に比べて柔らかくなりましたし、アスカが望むならいくらでももっといい男と付き合うことだってできるはずなんです」
「それは違うな、シンジ君」
加持は尚も漏らし続けるシンジの不安をピシャリと否定した。
シンジは顔を上げ、驚きを顔に浮かべて加持を見上げる。
「いい男やいい女っていうのは所詮主観的な物の見方だ。
顔が良いとか、性格が良いとかはあるかもしれない。けど、そんなものはその人のたった一面でしかないんだよ」
「そうでしょうか……」
「アスカの様子はどうなんだい?一緒に住んでる時と比べて何か変わったかい?」
「……いえ。自信はないですけど、たぶん変わってないと思います」
「おや、自信が無いのかい?」
「……いいえ、アスカは変わってないです」
「そうか。だが俺は変わったと思ってるよ」
加持のからかいを含んだ口調に、シンジは珍しくムッとしてやや強めに言い直す。が、加持は意地の悪い笑みを浮かべるとそれもまた否定した。それを聞いた途端、先ほどの強気も消え失せ、肩を落としてシンジはうつむいた。
「ちょっと、リョウジ!」
「言い方が悪かったな。
俺は、アスカは変わろうとしているんだと思っている」
「変わろう、ですか?」
「ああ、そうだ。
俺が思うに、君たち二人は変わらなさ過ぎたんだ。
エヴァに乗って使徒と戦う中で、アスカも君も深く傷ついた。体だけでなく心を、ね。
辛い毎日だっただろう?」
「そう…ですね。トウジやケンスケと友達になれましたし、楽しい事も多かったですけど……辛い事の方が多かった気がします」
「外から見ていてもそうだ。それはたぶん、俺よりもミサトの方が感じてたと思う」
「……」
「だから、サードインパクトを経験し、互いの感情を知り、互いの傷を共有し、君らは二人で暮らし始めた。
人は寂しがり屋だからな。一人では生きていけない。だから支えて欲しいと思うし支えたいと思うもんだ。
だがシンジ君、支え合って生きている、と言えば聞こえが良いが、君とアスカの生き方は傷の舐め合いそのものだ」
加持は厳しい口調で言い放った。これまで接してきた中で、シンジは何度も加持に叱咤されてきた。それはシンジを諭すものであったり、励ますもの、背中を押してくれるものと様々だった。そしてどれもに柔らかさが込められていた。
しかし今シンジを見据える加持の視線は冷たい。口調も硬質で、シンジは突き放される様な感覚を覚えた。
それと同時にシンジの中に裏切られた、との思いがくすぶり始める。
この人だけは自分を理解してくれている。自分を否定なんてしない。そんな考えがシンジの中には、無意識下ではあるが、確かに存在していた。
だが、根拠のない確信は今、あっさりと崩れ落ちた。失望がシンジの中に広がる。そしてそれと同時に怒りにも似た感情がシンジの体を震わせた。
「……加持さんに何が……」
「分かるさ。この六年間、ずっと監視してたからな」
「なっ……!」
「ちょっとアンタ!何を……」
「当然だろ?君らは最重要人物なんだ。まさか何も無しで解放されたと思ってたのかい?」
突然の加持の告白に、シンジだけでなく隣で聞いていたミサトも思わず大声を上げた。
それは本来ならばこの場で告げていい内容ではない。機密と、被観察者の心情という二つの面であってはならない事だった。
だが加持はそれを告げた。ミサトはシンジとは違った意味で呆然と加持の顔を見るが、その思惑は見て取れない。
加持は短くなったタバコをもみ消し、新たな一本に火を点ける。煙は真っ直ぐに空調に吸い込まれていった。
「ああ、流石に家の中までは監視はされてないから安心してくれ。だが六年間、君らが何処で誰と会い、何処で何をしていたかを審に観察していた。だがあれは支え合ってるというより寄りかかっている、と言った方が適切だろうな」
そんな事は無い、とシンジは否定したかった。だができない。
自分たちの在り方が周囲と違っている事はシンジ自身も気づいていた。そしてそれに気づかぬ振りをし続けてもいた。
それでもシンジは何とか否定の言葉を口にしようと試みる。
「僕は……」
「しかしだ、シンジ君。別に俺は君らの思いまで否定しようと思ってはないんだよ」
「え?」
突然加持の口調が柔らかくなり、シンジはパッと顔を上げる。
「きっかけや過程がどうであっても、アスカの事を一番理解しているのはシンジ君だろう。そして君の事を一番理解しているのも、恐らくアスカだ」
少々残念な気もするけどね。そう言って加持は笑う。
「君らは互いがいたからこそ、こうして俺やミサトと笑って話ができてるんだ。歪な形の愛かもしれない。けれども、だからこそ上手くやってこれたんじゃないか、と思うよ」
「……リョウジ、アンタ結局何が言いたい訳?」
「このままじゃいけないって事さ」
苦笑いに表情を歪め、加持はミサトにそれを向けると再び真面目な顔をしてシンジを見る。
「シンジ君もアスカも、法的に成人になる。加えて学校を卒業すればシンジ君は立派な社会人だ。今までとは比べ物にならないくらいに責任が覆い被さってくるだろうし、もしかしたら君を騙そうとしたり、昔の肩書きを利用しようとする奴らが寄ってくるかもしれない。
ま、そこら辺は俺らが言えた口じゃないけどな」
タバコを吹かし、一息入れる様に加持は煙を深く吐き出した。シンジは加持の言葉を黙って聞き、頭の中で何度も反芻する。
「周りに流されるだけだといつかは不幸になる。そうならないためにも君はもっと色んな事を知らなければならない。世の中の事もそうだし、アスカ以外の人の考え、感情、接し方……
今のシンジ君はアスカの事しか見えてない。アスカ以外の周囲にあまり関心が無いんじゃないかい?」
「そう、ですね……」
「人って存在は刻々と変わっていく。周囲の人が変われば、自然と自分の気持ちに変化も生じてくる。そしてそれが不安になってくるもんさ。今の君みたいにな」
「……」
「いつまでも同じ場所には留まれない。だから人は歩いていくんだ。少しでも良い明日をつかもうとしてね。
そしてアスカは君より先に動き出した」
「それが……アスカが僕と距離を置き始めたって事なんですか?」
「だろうな。
アスカも、賢いが少し視野が狭いところがあるからな。それにアスカは気づいて、そのままでいる事を嫌った」
シンジは黙って加持の話を聞いていた。そして同時に激しい自己嫌悪を感じてもいた。
これまでと同じ関係。シンジはアスカにそれを望んでいた。結婚は単なるけじめに過ぎない。
シンジにアスカを手放すつもりは無く、アスカも同じ気持ちだと思い込んでいた。アスカがいればそれで良く、他は些事。ただ人間らしい振りをしながら自分の見たいものだけを見て生きてきた。いや、それしかできなかった。
いつか見た、無数の意思と意志と遺志。おびただしい感情が渦を成し、乱雑に行き交い、だが一定の方向性を持って流れていた景色。L.C.Lと化した人の持つ善意と悪意に触れ、明確な記憶としては残っていないものの、シンジとアスカはそれらを覚えていた。そしてたまに夢で見て目が覚め、冷たい汗と恐怖に震えて、それを二人の体温で慰め合って生きてきた。それは二人で無ければならず、他の人に代える事ができない。
一方通行の感情に翻弄され、記憶は他人と深く触れ合うことを許さない。だから二人でずっとこうして生きていくのだとシンジは思い、それを真実だと思い込んでいた。
しかし、そうでは無かった。同じ場所へ居続けようとするシンジを尻目に、アスカは前へと進み始めた。
テーブルの下でギュッと強く拳を握り締め、逃げちゃダメだ、とシンジは昔自分に言い聞かせていた言葉を心の中で何度も繰り返す。その度に置いていかれそうな恐怖が鉛の様な重さを産み出した。
うつむき、眼を閉じるシンジの頭に大きな手が乗せられる。顔を上げると、優しい笑顔を浮かべた加持の顔があった。
「大丈夫さ。アスカの気持ちは変わってないよ」
夜も更け、騒がしいまでの話し声で溢れていた店内がいささか静かになっていく。
ミサトの手元には濃い色合いのカクテルが、加持の手の中には透明な焼酎が注がれていて、静かに杯を傾けていた。
「結婚か……この子たちももうそんな歳なのね」
正面で酔いつぶれて寝ているシンジの頭に、ミサトの手が触れる。
サラサラの髪を梳くようにして何度も撫で、その寝顔に眼を細めた。
「もう六年か……全てが終わってから」
ミサトのつぶやきに加持もならう。そして遠くを見るようにグラスの中の氷を見つめた。
カラン、と融けた氷が悲しげな音を鳴らし、その音を喉の奥へと流し込む。
「……ありがと」
「何がだ?」
「シンジ君の事。本当は私が諭してあげないといけなかったのに……
ホントいつになっても肝心なトコで役に立たないのね。嫌になるわ」
「止せよ。俺だってシンジ君には幸せになって欲しいからな。厳しい事を言うのはいつだって父親と兄貴の役目さ」
「それでも、よ。
短い時間だったけど、アタシとシンジ君とアスカは一緒に暮らしてきたわ。家族とも言えない家族ごっこだったけど……
それでもアタシがシンジ君にとって一番近い大人で、だから自分の事を棚に上げてでも間違いは正してあげないといけなかったのよ……」
そう言ってミサトはカクテルを一気に飲み干す。ほんのりと甘いはずのそれは、なぜか少し苦く感じられた。
「いいえ……本当はアタシが言ってあげたかったの。前は肝心な時に何も言ってあげられなくて、何もしてあげられなくて……ただ二人から逃げていただけだったから」
「ミサトは二人がどんな暮らしをしているか、知らなかったからな。
それに、近ければ近いほど言えない事もある。俺はずっと遠くからけしかけてただけだからな。仕方ないさ」
優しく加持はミサトを諭す。しかしミサトはそれにゆっくりと首を横に振った。
そして震える唇に、無け無しの力を込める。
「知らなかったんじゃないわ。知ろうとしなかっただけ。
怖かったのよ……シンジ君が、アスカがアタシを……恨んでるんじゃないかって……」
顔を伏せ、泣き出しそうな声でミサトは加持にそう漏らした。
両手で顔を覆い、体をテーブルにぶつけてグラスたちが不協和音を立てた。
「……シンジ君は君を恨んでたか?」
「えっ?」
加持の問い掛けにミサトは涙で濡れた顔を上げる。
「恨んでなかっただろ?じゃなきゃ君の事をまだ家族だと呼んでくれやしない」
「そういう子なのよ、この子は……」
「だが事実だ。あんな事があったのに、だ。普通ならもっと擦れてたり、シンジ君を敵の矢面に立たせて戦わせた俺たちを許しはしないだろうし、許したとしてもとても家族の様に付き合うなんてできない。
今日だってそうだろう。シンジ君の方からこうして誘ってきたんだ。それだけ君がまだ慕われてるって証拠さ」
「そう……かしら」
「ああ。家族ごっこ、と君は言ったが、それをシンジ君にも言えるかい?」
その問いに、ミサトは首を横に振った。それを見て加持はどうして、と尋ねる。
「だって……」
「シンジ君は家族、と言ったんだ。彼は君の事をごっこなんかじゃない、本当の家族だって心から信じてる。
大丈夫。君はあの時、できる限りの事はした。それはシンジ君にも、アスカにも伝わってるさ」
加持はミサトが飲んでいたカクテルと同じものを二つ、店員を呼び止めて注文する。程なく運ばれて並べられたそれをミサトは手に取る。
小さく何かを呟き、そしてゆっくりとグラスを傾けた。今度は本来の控えめな甘さが感じられた。
「もう、二人とも本当に離れていくのね」
「いつまでも庇護下には置いておけないさ。俺たちにできるのは見守る事と、今日みたいに悩んだ時に話を聞いてやることくらいしかできない」
「寂しいものね……」
「おいおい、寂しくなんかないさ」
ポツリと漏らしたミサトのつぶやきに、加持はおどけてみせた。
「俺たちは家族なんだ。その縁はいつまで経っても切れないさ」
「……そうね」
もう一度ミサトはカクテルグラスを傾けた。
そして、酔いの回った頭をコツン、と加持の肩へと預けた。
爽やかな風が流れる。
空に雲は一つも無く、焼けつくような日光が地面を照らすが、その熱を風が優しく包み込む。ザワザワと草木が鳴り、小高い丘に清涼さが染み渡る。
辺りには一人を除いて誰もいない。シンジは自然が奏でる音を聞きながら、自身は静かに手を合わせて眼を閉じていた。
シンジの前には三つの墓石が並んでいる。ユイのもの、ゲンドウのもの、そしてその間に建つ少しだけ小さな十字架。元々のユイの墓は壊れてしまったため、シンジは街の良く見えるこの場所に三人分を並べて建てた。いずれの墓にも遺体は無く、遺品も無い。ただ残された者のためだけの象徴としてそれらはここにある。
「綾波……」
墓を見下ろしながら、シンジはそっと名前を口にした。風がシンジの髪をなでるが返事は無い。供えられた線香からの煙が昇り、シンジもまたそれきり言葉を口にはしない。
静かな時間が流れる。シンジは真ん中の墓と向き合い、見つめ合うように視線を外さない。
やがてシンジはしゃがみこみ、すでに火の点いた線香の隣にもう一本立てて、本当はやり方が違うんだろうけど、とつぶやきながら手を合わせた。
「幸せになろうと思うんだ」
墓に向かってシンジは語りかける。
「ずっと……僕には無理だって思ってた。諦めてたけど、もう一度だけ頑張ってみようと思う。なれるかどうかは分からないけど、幸せになる、そのための努力はできるから……
だから綾波の分まで、なんて言えないけど、もうちょっとこの世界で足掻いてみることにしたんだ。たぶん、しばらくここには来れないと思うけど、でもまたいつか報告に、三人に話したいことができたらまた来ようと思う。その時まで……」
一瞬だけ強い風が吹く。そしてシンジの最後の言葉をかき消した。
墓に背を向け、シンジは歩き出した。しかしすぐ向こうに人影を認めて立ち止まり、だが再び歩き始める。
人影もまた歩き始め、シンジの方へと近づいていく。茶色がかった金髪が日光に反射してキラキラと輝く。二つの影が重なり、何かをシンジに向かってささやき、シンジもまた一言二言と言葉を返す。
彼女はシンジの横に並ぶと連れ添って駅へと向かって歩いていく。二人の手はしっかりと握られていた。
二次創作一覧に戻る