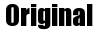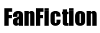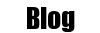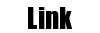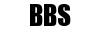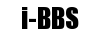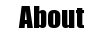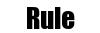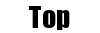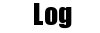あれはいつだっただろうか?
確か変な天気だったと思う。
と言っても特別変と言うほどでもなくて、天気雨だったはず。
空を見上げれば太陽が顔を覗かせていたのに、僕の顔にはぽつぽつと小さな雨粒が当たってた。
傘を持ってなかった僕は少し顔をしかめたけど、その内止むだろうと考えながら近くにあった喫茶店へと駆け込んだ。
幸いなことに雨はさほど強くなくて、鞄も僕も対して濡れずに済んだのはラッキーだった。
今日は特に予定も無いし、折角だからコーヒーでも飲みながら気分をいつもと変えて提出が間近のレポートでもやろうかと思いながら空いていた席へと足を運んだ。
そう、久しぶりに彼女と再会したのはそんな日だったんだ。
太陽の彼女
席に着くと注文を取りに来たウェイトレスさんにコーヒーを頼み、横の席に置いた鞄の中からファイルを取り出した。
ファイルの中には授業中に配布された数枚のプリントと板書を写したノートを取り出す。
そこには取り留めの無い文字が羅列していた。
当然ながら授業を受けてない人がこのノートを見たって全く理解できないだろうし、授業を比較的真面目に受けてる僕だって何を書いてるのかさっぱりだ。
(あの教授の授業分かりづらい上に板書も下手だもんな………)
心の中でその授業を担当している教授に愚痴をこぼしながらノートと睨めっこする。
まずは何を書いてるか理解しなければ、と思い、僕はノートの頭からひたすらプリントを参考に読み進めていく。
やっぱり気分を変えたのは正解だったな。
いつもより集中できた所為か、注文したコーヒーが置かれたことにも気付かず、半ば冷めかけたそれに気付いて一息ついた時にはレポートをするには十分な範囲まで進んでいた。
集中が切れると目元が急に重く感じた。
目元の筋肉を軽く揉み解すと、ぬるくなったコーヒーを口に含んだ。
コーヒーを飲みながら窓の外を見遣る。
いつの間にか雨は上がり、先ほどまで以上の暖かい日の光が道を照らしていた。
あの日から5年。
僕は19歳になり、十台最後の年を普通に過ごしている。
そこそこいいところの大学にも合格し、他の人と同じように大学生らしい生活をしてる。
季節は徐々にセカンドインパクト前に戻りつつあるらしく、昔のような格好じゃ今日は少し肌寒いくらいだ。
ふと横の席に置いた上着に目をやり、何気なく店内を見回す。
外観など気にせず入った割にはクラシックな感じがするお洒落な感じだ。
久々に当たりな日が来たようで、少し嬉しくなってまたコーヒーをすする。
このところあまりついていない日が続いていて、例えば、提出するはずのレポートを忘れたり、飲もうと思ったジュースを手を滑らせて落としたり………
そんな大したことじゃないんだけど、そんなことでも何日か続けばやっぱり気が滅入ったりすると思う。
そうして久しぶりにいい気分を味わっていた時、向かいに座ってる女の人が僕の目に入った。
座っているから分かりづらいけど、スカートの端から見える足から考えてかなりスタイルのいい人だ。
さらさらとした見事な金髪は決して染めたわけじゃなく、自然そのものに見えるから多分外国の方だと思う。
時折髪をかき上げる仕草が色っぽくて、いつの間にか僕はその人に見とれていた。
どれ位その人を見ていたのだろうか。
ずっとうつむいて何かしらの本―――どうも専門書らしい―――を読んでいて時々何かに苛立つかのように髪をかき上げていたのだけど、突然一息ついたのか、顔を上げた。
僕は心臓が止まるかと思った。
思わず僕は天井を見上げてしまった。右手で顔を覆いながら。
先ほどの言葉を僕は今ものすごく訂正したい気分だ。
どうも僕はついていない日がまだ続くらしい。
だってそこに居たのは僕が一番会いたくない人だったんだから。
ちなみにその女の人の名前は惣流・アスカ・ラングレーと言ったりする。
時間が止まったように僕達はお互い見つめあったまま固まっていた。
ただ、僕の場合は自分のツキの無さに、彼女の場合は見た感じでは単なる驚きが勝っていたようだけど。
彼女―――惣流アスカは呆然としたまま僕を見つめていた。
「……久しぶりだね、惣流さん。」
内心の思いを外に出さないよう極力気を付けながら声を掛けてみる。
ここまで見つめあったのに無かったことにするっていうのも変だし。
僕の呼びかけにようやく彼女は正気に戻ったらしい。
一時期とは違う、僕が知っている限り本来の彼女らしい笑顔で僕に笑いかけた。
「…そうね、久しぶり。シンジ。」
アスカとはあの後ほとんど会っていない。
全てが終わった後、彼女は両親の居るドイツへと送還され、そこで治療を受けることになったことは知っている。
そう、つまりはあの後彼女と話をしていないんだ。
だけど、その選択はどうやら間違ってはいなかったらしい。
あの時、僕らはお互いに何をやらかしてしまうか分からない状態だったから。
まぶしい位の輝きを取り戻せた彼女は僕にとってはまぶしすぎた。
だから、とりあえずの挨拶を済ませてこの場を離れたかったんだ。
じゃあ、と言って席を立とうとした。
少し状況としては変だけど、それは気にしないことにする。
でも、彼女はそれを許してくれないらしい。
「つれないわね、シンジ。久しぶりなんだから少し話をしましょうよ。」
「僕はそんなに話すことなんて無いよ。」
「別にいいわ。私の話を聞くだけでもいいから。」
ね、と片目をつむりながら手を合わせてくる。
昔じゃ考えられないアスカのそんな仕草に、僕は時間の流れを感じざるを得なかった。
自分は大人である、と行動の端々にそんな意思表示が見え隠れしていたあのアスカでは無かった。
辛かった。そんなアスカを見ることが。
でも、周りの目もあるし、ましてやアスカは飛び切りの美人であることには変わりはない。
そんな美人の頼みを断るなんて、どうも周りが許してはくれそうに無い。
……ぼくの気のせいかもしれないけど。
「……分かったよ。」
溜息をつきながら中腰になった体をまた椅子の上に乗せる。
それを見て、アスカは嬉しそうに笑顔を浮かべる。
「ね、今何をしてるの?大学生?」
「大学生だよ。他の人と同じようにそれらしい生活をしているよ。」
「バイトは?」
「特にしてない。」
「じゃあ、どうやって暮らしてるの?」
「奨学金とあのお金でやりくりしてるよ。」
あのお金―――ネルフから支給された退職金は僕達の手には余るほどの額だった。
普通に働いていては到底稼ぐことなど出来ない金額。
それにどんな思いが詰まっていたのだろうか?
同情?
贖罪?
それとももう関わりたくない、とばかりに手切れ金みたいなものなのかもしれない。
多分、様々な人の様々な思惑が入り混じっているんだろう。
でも、僕にはそんなものなんてどうでも良かった。
体力的に問題が無くなり、精神的にもある程度落ち着いた僕はそのお金をもらって第三新東京市を離れた。
思い出しただけでも吐き気がする。
そんなお金にも、そしてそれに頼らなければ生きていけない自分にも。
でも何故だかアルバイトをしたりしてそのお金を使わないで生きていく気にはならなかった。
そこまで考えて気が付いた。
「さっきから僕の話しかしてないじゃないか。」
「いいじゃない。どんな風にシンジが過ごしてきたか気になるんだし。」
「もう話すことなんて無いよ。」
これで話は終わりだと言わんばかりに僕は窓の外を見た。
視線を外したからアスカがどんな表情を浮かべているのかは分からない。だけど、きっと罵声が飛んでくるに違いない。
いや、今のアスカなら悲しそうな顔をしているかもしれない。
どちらにしろ、これで彼女とは離れられるだろう。
ちらりとアスカの方を見てみる。
そこにはそんな僕の期待を裏切って、特に気にした風も無く僕の方を見ているアスカがいた。
「じゃあ、今度は私の番ね。」
そう言うと、今度は自分があの後どんな風に過ごしてきたかを話し始めた。
僕はそれを適当に相槌を打ちながら聞いていた。
その話によると、ドイツに送られた彼女は両親の元で療養していたらしい。
大分精神的に不安定だったけど、それでも母親の献身的な介護と努力で回復していった。
昔は好きじゃなかったけど、今ではとても母親に感謝していると。
嬉しそうに語ってくれた。
今はどこかの研究所に勤めていて、その関係で日本に来たそうだ。
そこまで色々身振りを交えながらマシンガンのように一気に話し終えると、今度は僕に話を振る。
「ところで、この後シンジは暇?」
「……暇じゃないよ。」
「嘘ね。」
その瞬間、僕は自分が凍りついたかのような感覚に陥った。
間髪いれずにそう断言したアスカは昔、使徒と戦っていた時のような鋭い目をしていた。
メデューサに魅入られた様に、僕は瞬きすら許されなかった。
背筋に冷たい汗が流れる。
だけど、その緊張は長くは続かなかった。
アスカの顔が緩む。
さっきとはうって変わって笑顔を浮かべた。
それを見て、僕は一気に体の力が抜けていった。
「暇よね?」
「………うん、暇だよ。」
「良かった。ちょっと付き合って欲しいんだけど。」
アスカはあふれんばかりの笑顔を浮かべて僕の返事も聞かずに伝票を持って席を立とうとする。
それを見ていると、さっきのアスカは何だったんだろうか、思わず自分の目を疑ってしまうよ。
何か反論をしようと思ったけど、さっきのアスカの目がちらついて、結局僕は何も言えず、荷物を抱えてレジのアスカの元へ向かうことしか出来なかった。
「それで、どうしてここに?」
僕がそう洩らすのも無理は無いと思う。
だってアスカに連れて来られたのはアスカの滞在しているホテルだったのだから。
どういうつもりか、と僕は目でアスカに問いかけた。
そのアスカはというと、スプリングコートをベッドに脱ぎ捨て、ボフッとベッドの上へと飛び乗った。
「別に深い意味は無いわ、と言っても信じないわよね?」
「まあね。惣流さんがどういうつもりかは知らないけど、普通は男を連れてホテルに来るっていうことはそういうことを意味するよ?」
「じゃあ、する?」
そう言うと、昔僕をからかっていた時のように胸元を軽く広げて誘惑してきた。
それに僕は溜息で返事をする。
「へえ、ちょっとは成長したのね。てっきり顔を赤くしてうろたえるかと思ったわ。」
「いい加減僕も二十歳になろうかっていう年だからね。その手には乗らないよ。」
「その割には止まったままなのね。」
そう言うとまた僕を見つめた。あの目で。
言葉とともに全てが見透かされたような気がする。
だけど、二回目で多少なりとも慣れたのか、喫茶店の時みたいに固まることは無かったのは幸いだと思う。
僕は出来るだけ内心の動揺を悟られないよう、努めて冷静に言葉を返した。
嘲りを含めて。
それは自分への嘲笑だったのかもしれない。
「止まったままって、何のことさ?」
「認めなさいよ、シンジ。いえ、バカシンジって言うべきかしら?」
「僕には惣流さんが何を言ってるのか分からないよ。」
「分かってるはずよ。そうでなかったら、どうしてアンタはそんなに動揺してるの?」
「動揺?僕が?どうして動揺する必要があるのさ?」
「いい加減誤魔化すのは止めなさいよ。」
「いい加減にするのはそっちだ!悪いけどもう帰らせてもらうよ。」
大声で叫ぶと僕は椅子に置いてあった荷物を乱暴に抱えてドアへと向かった。
いい加減不愉快だった。
アスカと話すのも、顔を見るのも、そしてここに居るのも。
「シンジ。」
アスカは去り際に僕に何かを投げてきた。
目前に迫ったそれに思わず僕は受け取ってしまった。
「私は後3日くらい日本にいるわ。それはその間の連絡先。別にここに来てもいいけど。」
「ありがたい申し出だけどね。君と会うことは無いだろうね。」
「そう。それならそれでいいわ。」
そんな言葉とは裏腹に、そう言ったアスカの顔はどこか寂しげだった。
それがその日、最後に見たアスカの顔だった。
僕はホテルを出て、もうすっかり暮れてしまって暗くなった道を一人で歩いていた。
頭に血が上ってアスカと別れた僕だけど、少しひんやりとした夜道はそんな僕の頭を少しずつ冷やしていった。
怒るのは図星を指されたからだ。
どこかで聞いた言葉を頭の中で反芻しながら考えていると、なるほど、確かにそうだと思う。
そう、アスカの言う通り僕は止まっているのだ。5年前のあの日から。
ただ体だけが成長して、心の時間はあの時のまま歩みを止めている。
多分それは僕も気付いていたのだと思う。
だから、それを指摘された時、僕は平静ではいられなくなった。
怖かったんだと思う。それを認めてしまうのが、あの頃の自分だと言われるのが。
僕は14歳の僕が嫌いだ。それはその当時から変わらないと思う。
そんな僕と一緒と言われるのが我慢できなかったんだろうか?
でも、やってることはそんな僕と変わらなかった。
だって最後にしたことはその場から逃げ出すことだったんだから。
都合が悪い事を言われるとすぐ逃げ出す。
まるで子供だ。いや、あの頃よりもっと悪いかも知れない。
成長なんてものがまるで無いじゃないか。
アスカに言われ、自分でも再認識したよ。
何も変わっていない。情けないほどに僕はバカシンジのままだった。
自らの情けなさを嘲りながら夜空を見上げてみる。
そこには昼間にあった雲はどこにも無く、だけど、見えるはずの星は曇っていてぼんやりとしか見えなかった。
翌日、重い気持ちのまま僕はいつもと同じように大学へと向かっていた。
本当は昨日のうちにアスカに連絡をとって謝りたかった。
だけど、あれだけ言って舌の根も乾かぬうちに、というのも何だかなぁ、と思って結局出来なかった。
……やっぱり情けない。
本当にそう思うけど、今日こそは連絡を取りたい。
そしてきちんと認めて謝罪したかった。
それは昨日のことだけではなく、5年前についても色々と、だ。
じゃないと、僕はずっと立ち止まったままになってしまうと思うから。
そのことばかりが気になって全然授業も耳に入らなかった。
どうも緊張してるらしい。まだ一限の授業が始まったばかりなのに。
その日は3限までしか授業は無かったんだけど、結局どの時間も同じようなものだった。
そして授業が終わった瞬間、僕は講義室を飛び出した。
まずは家に帰って荷物を置いて、そしてアスカと連絡を取る。
そう考えた僕はまだ人もまばらなキャンパスを走り出した。
「あら、シンジじゃない。」
でもその足はすぐに止まる事になった。
「ア…惣流さん!どうしてここに!?」
「それはこっちのセリフよ。どうしてアンタがここにいんのよ?まさかアンタの通ってるのってここ?」
「そうだよ。」
「へえ、すごいじゃない。そこそこ、だなんて言ってたけど、ここでそこそこだなんて言ってたら怒られるわよ。」
そう、ここは第二東大―――まあ、僕が通ってるんだけど―――自分でもよく受かったなぁと思うし、でも競争率はそんなに高くないから周りが考えてるほど難しくはないと思う。
話が逸れた。褒められるのは悪くないけど今はそれはどうでもいい。
ちょうどいい機会だ。昨日の事を謝らなきゃ。
そう思うけど、いざ言葉にしようとすると中々出てきてくれない。
(くそっ!何でだよ!?)
心臓が激しく脈打ち、舌が乾く。
今まで以上の緊張に内心で悪態をついた。
深呼吸をして気分を落ち着ける。
そうだ、落ち着け。
落ち着いたところで声を掛けよう………と思ったところで、またアスカに先を越された。
「話があるんだけど、ちょっと歩きましょう?」
「…いいよ。僕も話したいことがあったんだ。」
「そう?ならちょうどいいわね。」
そして僕らは近くを歩いて回った。
話があるって言ってたアスカだったけど、中々切り出そうとしない。
でも、もうしばらく待とうと思う。さっきの僕もそうだったから。
10分くらい歩いただろうか?大学の周りを半分くらい回ったところでようやくアスカが口を開いた。
「アタシはね、ずっとアンタのことが分からなかったの。」
「僕のこと?」
「そう。この前話した通り、ドイツに帰った当初のアタシは精神的に大分ひどいものだったわ。アタシはよく覚えてないんだけど、ママの話じゃよく夜中に叫び出したらしいの。アンタを殺してやる、てね。」
「………」
「他にも色々おかしかったんだけどね。そこら辺はママのおかげで回復していったわ。アンタのことについても徐々に納まっていったの。
だけど、それは悪夢として納まっただけ。色々な思いが中へ中へと向かっていったわ。アンタに対していいものも悪いものも一まとめにね。それで結局ぐちゃぐちゃになっちゃって訳分かんなくなっちゃったのよね。
あ、今のは勿論私の勝手な推測。専門じゃないからよく分かんないけど、そうじゃないか、って何となく思うの。」
「…それで日本に?」
「そうよ。しばらくは別に何とも思ってなかったんだけど、最近になってよくまたあの時の夢を見るようになったわ。
多分、無理やり押し込めたような状態だったから無理が出てきたのね。
でもあの時の夢だけじゃないわ。アンタもよく出てくるようになったの。」
「僕が?」
「ええ。
アンタの首を絞めて殺して暗い笑いを上げる夢を見たし、アンタに抱かれて悦びの声を上げる夢も見たことだってあるわ。
それでアタシはいよいよ分からなくなったわ。アンタをどう思ってるのか。
ちょうどその時、アタシに日本行きの話が来たの。
短い期間だけど、自分の事を見つめなおすのに日本行きはいい機会だと思ったわ。」
「あの喫茶店で僕に会ったのも狙ってたの?」
まただ。
自分でも嫌な言い方だと思う。
先ほどまでとは変わって冷たい声を出してしまったことに自分も驚き、僕は気まずさを感じてわずかに視線を逸らした。
それでも彼女は気にした風は無く、笑いながら僕の問いかけを否定した。
「まさか。でもそう言えるかもしれないわね。アンタの場所を探していたのは事実だから。
日本に来る前に研究の合間をぬって色々調べたの。それで第二東京に住んでるところまでは分かったのよ。でもそこまでで時間切れ。
その後はこっちに着いてから調べようとしたけど時間が無くて、この前やっと時間が取れたのよ。それでどうしようか考えようと喫茶店に入ったのよ。まさかそこでアンタに会うとは夢にも思って無かったわ。」
本気で神様を信じてみようかと思った、と言ってアスカは苦笑いを浮かべながら僕の方を見た。
「ゴメン……。」
そんな僕から出てきたのは昔と何ら変わりない薄っぺらな謝罪の言葉だった。
「謝らなくてもいいわ。
それにしてもアンタ、ホントに変わんないわねぇ。
いえ、それは私もよね。」
苦笑いの次にアスカの顔に浮かんだのは、あの頃には一度も見たことの無い自嘲の笑みだった。
その表情に僕は胸が押しつぶされそうな感覚になる。
お願いだから、そんな顔をしないで欲しい。
そんな思いは僕の口から出ることなく、そのままアスカは言葉を続けた。
「結局、アタシもシンジと変わんないのよね。口では偉そうなこと言っておきながらさ。」
背中を見せるアスカの肩がわずかに震えたのを僕は見逃さなかった。
少しずつアスカの声が大きくなっていった。
「アタシの中の時間もあの時から全く動いてないのよ。
何よ、認めなさいって。自分は認めてる気になってて、人には偉そうで、ほんっとに反吐が出るわ!
結局私もシンジに全て押し付けて!アンタに会えば何か分かるって勝手に思い込んでて!土足で人の心の中に踏み込んで!何様よ!
私の方が昔のままなのよ!!」
僕は気がつけば後ろからアスカを抱きしめていた。
もう、そんなアスカを見ていたくなかったから。慟哭をあげる彼女を楽にしてあげたかったから。
「アスカ。」
「……何よ…」
「もう、そんなこと言わないで。自分を自分でおとしめないで。
昨日、ホテルから帰りながら考えてたんだ。僕はずっと逃げてたんだ。自分の問題に気付いていながら気付かない振りをしていたんだ。
それをアスカが気付かせてくれた。
だから感謝してるんだ。
アスカのおかげで僕はちゃんと少しあの頃から前に進めたんだ。まだ小さな一歩だけど……。
アスカは僕よりずっと早くそれに向き合えていたんだ。それはすごいことなんだ。
だから……そんなこと言わないで………。」
僕は痛いくらいにアスカを抱きしめた。
心がこれ以上痛くならないように。
「……私はシンジが憎かった。
シンジはアタシが憎くないの?」
ホテルで僕らはお互いの体温を感じていた。
抱きしめながら、アスカが不安げに尋ねてきた。
「多分、憎かったんだと思う。でも、それと同じくらい好きなんだと思う。
それに気付くのが怖かったんだ。何が起こるか分からないから。
だから、アスカに会いたくなかった。アスカが嫌いなんだと思い込もうと、自分を誤魔化そうとした。
でも、それじゃ意味無いんだ。何も変わらないんだ。
急には無理かも知れない。それでも変わる努力はしていこうと思うんだ。
アスカも、僕と一緒にやっていこう……」
そして僕はアスカに口づけて、もう一度、アスカのぬくもりを感じようと体を重ねた。
「じゃ、そろそろ行くわ。」
荷物を僕から受け取ると、アスカは僕にそう告げた。
「うん、今度は僕がそっちに行くよ。」
「あんまり待たせんじゃないわよ。アタシは気が短いんだからね。」
「分かってるよ。今度の夏休みには遊びに行くから。」
多くの人で混雑した空港の中、アスカの背中が少しずつ小さくなっていく。
だけども僕の中に寂しさは無かった。
僕達は約束したから。どこに居ようとも二人で一緒に歩みを進めていくと。
その歩みはとても遅いかもしれない。でも、確実に失った時間を取り戻すことが出来ると僕は信じている。
しばらくロビーで時間を潰した後、空港の屋上に向かう。
ドアを開けた瞬間、眩いばかりの光が照らしつける。
その中を彼女を乗せた飛行機が横切っていく。
身を焼かんばかりにさんさんと降り注ぐ日の光は、まるでアスカを、元気だった頃の、一番輝いていた頃のアスカを象徴しているかのように僕は感じられた。
今度出会うときはきっと当時以上に輝いているだろう。
「さて、バイトしないとな。」
全身で光を浴びるように大きく背伸びをすると、僕は空港を後にした。
まずは一歩を踏み出すために。
終
二次創作一覧に戻る